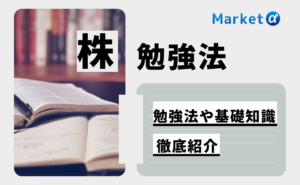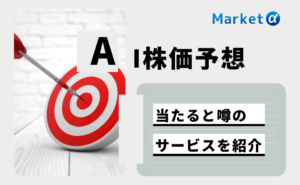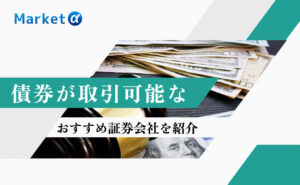資産運用・投資おすすめランキング13選|選び方やポイントを徹底解説!
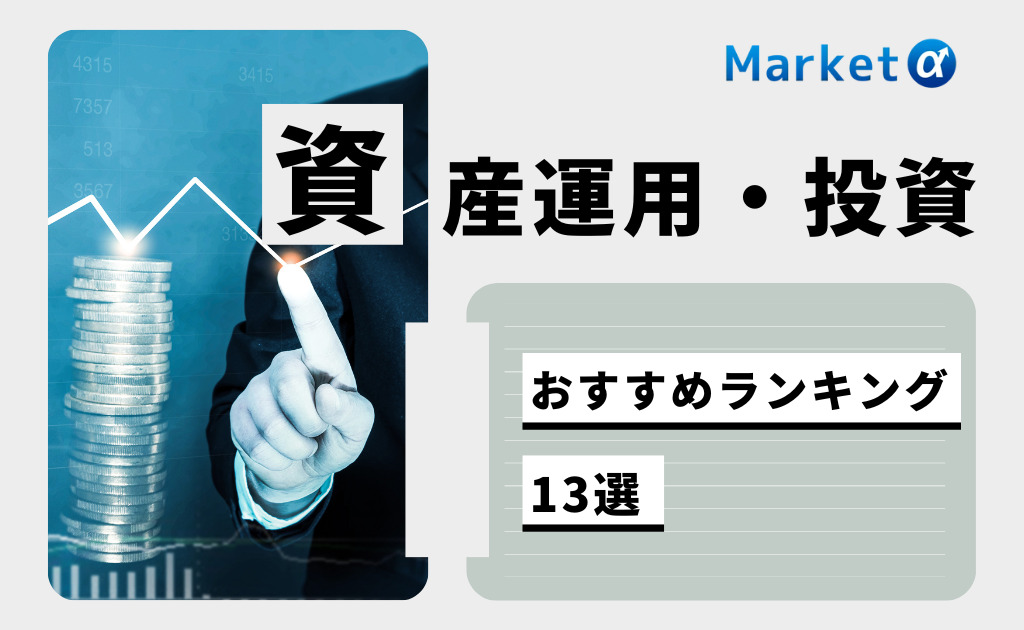
資産運用や投資にはさまざまな種類があり、どのように選び分ければ良いのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
その場合は、まず初心者・中級者といった投資レベルを把握することが大切です。
さらにリスクリターンや運用コスト、運用期間といった基準で選び分けていくと、自分に合う運用方法が見つかりやすくなります。
本記事では、初心者向け・中級者向けの資産運用方法や選び方、失敗を避ける方法について解説します。
- 資産運用の手段には、投資レベルに合わせたさまざまな方法が存在する
- 初心者向けと中級者向けに適切な運用方法を13種類紹介
- 選び方のポイントを押さえておくと、自分に合う運用方法が見つかりやすい
- 少額投資や分散投資を心がけて運用時の失敗を減らそう
- 資産運用を行うにあたって必要なおすすめの証券会社を紹介
これから資産運用や投資を始めたい方には、SBI証券が最適です。
SBI証券は株式やFX、債券、投資信託など幅広い金融商品を扱っています。
取引手数料も業界最安値クラスを誇るため、メイン口座としてもサブ口座としても使い勝手に優れるでしょう。
興味のある方は、SBI証券公式サイトをチェックしてみてください。

Marketαでは公式LINEで仮想通貨(暗号資産)に関する情報を随時配信しています。
最新情報やキャンペーンを発信していますので、ぜひ登録しておいて見て下さい。
資産運用・投資におすすめの方法一覧
まずは、おすすめの資産運用や投資方法の一覧表をご紹介します。
| 運用方法 | 投資レベル | 難易度 | 自由度※ | 運用期間 |
|---|---|---|---|---|
| NISA・つみたてNISA | 初心者向け | 中 | 低 | 自在 |
| iDeCo | 初心者向け | 中 | 低 | 長期 |
| 投資信託・ETF | 初心者向け | 中 | 高 | 自在 |
| ミニ株 | 初心者向け | 中 | 中 | 自在 |
| ロボアドバイザー | 初心者向け | 低 | 低 | 長期 |
| 債券 | 初心者向け | 低 | 低 | 長期 |
| 貯蓄型保険 | 初心者向け | 中 | 低 | 長期 |
| 個別株投資 | 中級者向け | 高 | 高 | 自在 |
| FX | 中級者向け | 高 | 高 | 自在 |
| 外貨預金 | 中級者向け | 低 | 中 | 長期 |
| 仮想通貨 | 中級者向け | 高 | 高 | 自在 |
| 不動産投資 | 中級者向け | 高 | 中 | 長期 |
| ソーシャルレンディング | 中級者向け | 低 | 低 | 長期 |
上記のように、投資レベルごとに適した複数の運用方法があります。
とはいえ、同じ投資レベルの運用方法でも、難易度や自由度、運用期間がそれぞれ異なるため、いろいろな方法を試しつつ自分に合うものを選択する必要があるでしょう。
各運用方法の詳細については、後ほど詳しく解説します。
資産運用・投資をするときの選び方
運用方法を選ぶときのポイントは次の通りです。
- 期待リターン
- リスク許容度
- 運用時のコスト
- 運用期間
- 運用しやすさ
- 税制度
- 自分で運用するかどうか
期待リターン
資産運用や投資によってどの程度の収益を確保するのか、期待リターンを定めましょう。
期待リターンは「利回り」とも呼ばれます。
たとえば、100万円を投資して1年後に元利合計(元本+利益)が105万円になったとすると、1年間に5万円の利益が発生したことになるので、年間利回りは5%です。
運用する金融商品によって平均利回りが異なるものの、一般的に年間4~5%の利回りを確保できれば成功だと言われています。
まずはどの程度のリターン(利回り)を確保したいのかを決め、その目標を達成できそうな運用方法を選ぶと良いでしょう。
リスク許容度
リスク許容度とは、リターンがマイナスに振れてしまった場合に、どの程度の損失を受け入れるかという度合いです。
一部の金融商品を除き、基本的に資産運用や投資では元本割れのリスクがあるため、利益を得られることもあれば、反対に損失が発生してしまう場面もあります。
そのため、どの程度の損失までなら問題なく運用を継続できるかという点を明確にしておきましょう。
ほとんどの場合、大きなリターンを期待できる運用方法ほどリスクが高く、リターンの小さい運用方法ほどリスクが低くなります。
リスク許容度があまり高くない方は、ローリスクローリターンの運用方法を選ぶのが無難です。
運用時のコスト
資産運用や投資では、取引手数料や銘柄の維持手数料、証券口座の入出金手数料といったコストがかかります。
運用する金融商品によって手数料の種類や割合が異なるため、事前によく理解しておくことが大切です。
また、同じ金融商品を運用するにしても、利用する証券会社や金融機関によって手数料に差があるので、できるだけコストを抑えられるところを選びましょう。
運用期間
運用期間も金融商品によって大きな違いがあります。
たとえば、短期にも長期にも対応しやすい個別株投資やFXといった金融商品がある一方で、基本的に長期運用にしか対応できないiDeCoや債券などの種別も存在します。
まずは自分の投資スタイルを短期・中期・長期の3つに分け、それに合う運用方法を選択しましょう。
- 短期:数分~1ヶ月程度でポジション(保有銘柄)を決済
- 中期:1つの銘柄を1~3年程度保有し、頃合いを見計らって決済
- 長期:1つの銘柄を5~10年以上保有
運用しやすさ
資産運用や投資に慣れない方は、運用する際の条件が少ない金融商品を選ぶのも方法のひとつです。
そのほうが運用しやすく、早い段階で資産運用や投資の環境に慣れることができるからです。
たとえば、個人型確定拠出年金とも呼ばれるiDeCoには、投資できる銘柄が限られていたり、被保険者の種別によって拠出限度額が異なったりするほか、60歳になるまで給付金を受け取れないといったさまざまな条件があります。
iDeCoは初心者向けの運用方法ですが、一から始めるなら、もう少し条件の少ないものからスタートするほうが簡単です。
税制度
株式投資や投資信託の税金は一律20.315%、仮想通貨は15~55%の累進課税が採用されているなど、運用する金融商品によって税制度が異なります。
金融商品ごとの税制度も事前によくチェックしておきましょう。
そのなかでもNISAやつみたてNISAは、一定の条件を満たすと非課税となるため、加入しておいて損はありません。
自分で運用するかどうか
最後に、自分で運用するか、それとも別の人や便利なツールに運用を任せるかを決定しましょう。
売買のタイミングを自分で判断する取引方法のことを裁量取引といいます。
一方、運用の大半をプロやAIに任せる投資信託やロボットアドバイザー、事前に設定したプログラム通りに売買を行う自動売買システムなど、自分以外に運用を任せる取引方法も存在します。
普段は仕事や家事で忙しい方なら、他者に運用を任せられる金融商品のほうが合っているでしょう。
数ある証券会社のなかでもSBI証券なら、幅広い金融商品の選択肢から自分に合うものを選べます。
口座開設手数料は無料なので、さっそくSBI証券をチェックし、お気に入りの金融商品や銘柄を探してみてはいかがでしょうか。
資産運用・投資で失敗しないためのポイント
続いては、資産運用や投資で失敗しないためのポイントを5つご紹介します。
- 少額の元手で始める
- 投資先を分散する
- 短期的な値動きに一喜一憂しない
- 金融リテラシーを身に付ける
- 周りの意見に耳を傾ける
少額の元手で始める
資産運用や投資に活用する元手は、余裕のある範囲で少額の資金を捻出しましょう。
慣れないうちから高額な元手で資産運用を行ってしまうと、思わぬ値下がりや暴落によって大きな損失が発生してしまう可能性があります。
自分の投資スタイルが確立するまでの間は、リスクを抑えられる少額投資が最適です。
最近では、数百円程度で投資できる金融商品や手法が増えています。
投資先を分散する
失敗を回避するには投資先を分散するのも効果的です。
投資先を多方面に分散するほうが、1つの銘柄に資金を集中させるよりもリスクを抑えられます。
たとえば、Aという銘柄の価格がひとたび暴落すると、途端に大きな損失を被りますが、A・B・Cの3つの銘柄に分散投資しておくと、BやCの値上がりによってAの損失をカバーできるでしょう。
金融商品の種別や投資する地域、運用期間など、さまざまな要素を分散するほどリスク抑制の効果が高まります。
短期的な値動きに一喜一憂しない
資産運用や投資を始めたばかりの頃は、日々の価格変動に神経をとがらせてしまいがちですが、短期的な値動きに一喜一憂しないことが大切です。
特に、特定の銘柄を長期運用する場合、一時的に価格が大きく下がったからといって、その時点で銘柄を手放してしまうと元も子もありません。
長期投資では複利効果によって資産を倍々に増やすのが目的のひとつなので、短期間で売却してしまうと、その果実を得られなくなってしまいます。
また、短期投資を行う場合でも、値動きのことばかり考えていると精神的な負担が増します。
資産運用や投資では、勝つこともあれば負けることもあることをよく理解して、淡々と取引を実行していく必要があります。
金融リテラシーを身に付ける
どのような運用方法を採用するかにかかわらず、絶対に必要となるのが金融リテラシーです。
金融リテラシーとは、資産運用や投資を行ううえで必要となる知識や教養を意味します。
資産運用や投資を行う際は、パフォーマンスの高い銘柄を選んだり、最適なタイミングで売買を行ったりしなければならず、その判断を行うために金融リテラシーが必要となります。
反対に、やみくもに資産運用や投資を行った場合、利益よりも損失が膨らんでしまうことが多いので注意が必要です。
あらかじめ証券会社の学習コンテンツやYouTubeの投資向け動画などを参考に、基本的な知識を習得しておきましょう。
周りの意見に耳を傾ける
投資対象となる金融商品や個別銘柄を選ぶ際は、インターネット上の評判や口コミのほか、実際に資産運用を行っている第三者の意見などを参考にすることも大切です。
投資する対象によっては、収益性が期待できない怪しい金融商品や銘柄も存在しているからです。
たとえば、運用方法のひとつであるソーシャルレンディングは、預貯金よりも高いリターンが期待できるという理由で2010年代あたりから注目を集め始めました。
しかし、次々と新しいサービス会社が生まれるなか、融資先の貸し倒れや延滞が続々と発生し、それが原因で倒産してしまったサービス会社も存在します。
ソーシャルレンディングの仕組みそのものが悪いわけではありませんが、運用する際にはサービス会社や融資先の信頼性を十分にチェックする必要があるでしょう。
このような際に、周りの意見をしっかりと聞いたうえで適切な判断を下すことが重要となります。
さらに資産運用や投資のコツを学びたい方には、SBI証券が最適です。
SBI証券には豊富な学習コンテンツが用意されているため、投資をしながら同時に金融リテラシーを向上できます。
このような学習コンテンツは無料で利用できるので、詳しくは、SBI証券公式サイトをチェックしてみてください。
初心者向けの資産運用おすすめランキング
初心者向けにおすすめする運用方法は次の7つです。
- NISA・つみたてNISA
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 投資信託・ETF
- ミニ株(単元未満株)
- ロボアドバイザー
- 債券
- 貯蓄型保険
1. NISA・つみたてNISA
少額投資非課税制度という名称で、金融庁によって2014年にスタートした運用方法です。
NISAの場合、年間120万円の投資枠で発生した利益を、最長5年にわたって非課税にできます。
金融庁が認可した投資信託やETFが投資対象となります。
そのNISAをより長期投資に適した制度に改良したのが、つみたてNISAです。
つみたてNISAだと投資枠が年間40万円に縮小されますが、最長20年にわたって運用益を非課税にできます。
つまり、月間33,000円ほど投資信託の積み立てを行うと、つみたてNISAを最大限に活用できるということです。
積立投資を行うには、銘柄を購入する頻度と1回あたりの購入金額を設定するだけで済むため、初心者の方でも簡単に始められます。
2. iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、金融商品を積み立てる形で定期的に資金を拠出すると、国民年金や厚生年金とは別に給付を受けられる制度です。
拠出した資金は60歳になるまで払い戻せない条件があるものの、将来受け取る年金受給額を引き上げられるメリットがあります。
企業型確定拠出年金と仕組みはほとんど同じですが、iDeCoの場合は、運用する金融商品を自分で自由に選べます。
3. 投資信託・ETF
投資信託は、ファンドと呼ばれる特定の金融商品に多数の投資家が資金を出し合い、プロのファンドマネージャーに運用をお任せする方法です。
資金を投じた投資家に対しては、投資額に応じて定期的な分配金が配られます。
ETFは、その投資信託を証券取引所に上場した金融商品を指します。
上場しているので金融機関の窓口にいかずとも、ネット証券などで自由に売買できるほか、株式投資やFXのようにリアルタイムのチャートを確認しながら取引の判断が可能です。
4. ミニ株(単元未満株)
株式投資では本来、単元(100株)ごとに取引する必要があります。
最低100株を購入しようと思うと、銘柄によっては数十万円の元手が必要になることから、株式投資はハードルが高いと言われてきました。
その株式投資を、100株未満から購入できるようにしたのがミニ株(単元未満株)です。
証券会社によっては1株から購入できる場合もあり、最小500円程度の元手で済みます。
5. ロボアドバイザー
ロボアドバイザーとは、事前に簡単な質問に答えるだけで、AIが自分に合う投資対象を提案してくれるサービスです。
また、実際の運用まで肩代わりしてくれるケースもあります。
投資対象は投資信託やETFの場合がほとんどですが、自分で銘柄を探す必要がなく、細かい運用サポートまで行ってくれるため、投資信託よりもさらに初心者向けだといえます。
また、長期運用が前提となり、ほとんど放置していても運用できるため、忙しい方にも人気です。
6. 債券
債券とは、国や企業がお金を借りるために発行する有価証券です。
国が発行したものを国債、企業が発行したものを社債と呼びます。
特に国債の場合は、一国の破綻リスクが極めて低いこともあり、原則として元本が保証されています。
リスクが低い分リターンも限られていますが、安全資産としてポートフォリオに組み入れておくと、資産運用におけるリスクを和らげられます。
7. 貯蓄型保険
貯蓄型保険とは、契約満了時に返戻金を受け取れる貯蓄性のある生命保険です。
生命保険にはほかにも掛け捨てタイプがあり、こちらは死亡や障害状態になると保険金が受け取れる一方で、契約中に事故や病気がないと支払った保険料は戻ってきません。
その点、貯蓄型保険なら、万一の事故や病気の際に保険金が支払われるほか、事故や病気がなくても契約後に支払った保険料が返戻金として戻ってきます。
その返戻金は、元金に利息がプラスされて戻ってくるため、投資性も兼ね備えています。
ただし、掛け捨てタイプよりも月々の保険料が高いため、より計画的に活用する必要があるでしょう。
SBI証券なら、ここまでにご紹介したほとんどの金融商品を取り扱っています。
さまざまな金融商品で自分好みのポートフォリオを構築できるのが、SBI証券の最大の魅力です。
詳しくは、SBI証券公式サイトをチェックしてみてください。
中級者向けの資産運用おすすめランキング
中級者向けにおすすめする運用方法は次の6つです。
- 個別株投資
- FX
- 外貨預金
- 仮想通貨
- 不動産投資
- ソーシャルレンディング
1. 個別株投資
個別株投資とは、個別の株式銘柄を自分で探して運用する方法です。
株式を発行している各企業は、設備投資や市場拡大などで業績が伸びれば、中長期的に大きく株価が上昇する傾向にあります。
そのため、将来的に企業価値が高まりそうな銘柄を選別することが大切です。
とはいえ国内株だけでも数千種類以上の銘柄が存在するため、そのなかから目的の銘柄を探すには、企業の決算情報や会社四季報といったさまざまな情報を調べなければなりません。
初心者向けの運用方法に比べて、やや難易度が高いといえるでしょう。
2. FX
FXとは、2国間の通貨ペアによって利益を獲得する運用方法です。
たとえば米ドル円は、アメリカのドルと日本の円がペアになっており、それぞれの需給バランスによって価格(為替)が変動します。
米ドル円を扱うなら、米ドルの価値が低いとき(ドル安円高)に日本円で米ドルを購入し、その価値が下がったタイミング(ドル高円安)に米ドルを売ると、売却益を得られる仕組みです。
また、2国間の金利差によって利益が発生するスワップポイントがあるのも特徴です。
スワップポイント狙いで運用する場合、購入した銘柄を保有しているだけで利益が発生します。
ただし、スワップポイントで利益を得るには、日本円のような金利の低い通貨を売り、それよりも金利の高い通貨を買う必要があります。
3. 外貨預金
外貨預金とは、日本円を外貨に両替し、そのまま銀行に預金して利息を受け取る方法です。
近年の日本はしばらく低金利状態が続いているため、銀行にお金を預けていてもほとんど利息を受け取れません。
そこで、日本よりも金利の高い海外(主にアメリカ)で預金することで、より高い利息を受け取れるようになります。
ただし、FXと同様、各国の通貨は日々価格が変動しているため、預け入れたときよりも引き出す際に円高になっていると、為替差損が発生してしまう可能性があります。
このような為替変動を予測する必要がある以上、初心者向けの運用方法よりも難易度が高いといえるでしょう。
4. 仮想通貨
2022年11月5日時点で、仮想通貨には20,000以上の種類が存在します。
最も有名なビットコインも仮想通貨の銘柄のひとつです。
仮想通貨の価格は日々変動しているため、安いタイミングで買って、高くなってから売ると売買益を獲得できます。
仮想通貨は株式やFXに比べて価格変動が激しいため、値上がりしたときに大きな利益が期待できる一方で、多額の損失を被るリスクもあります。
また、最近では仮想通貨を貸し出して利息収入を得る「仮想通貨レンディング」や、月々500円程度から始められる「積み立てサービス」など、運用方法が多様化しています。
5. 不動産投資
不動産投資とは、土地や建物を購入して、第三者に貸し出して利益を得る運用方法です。
たとえば、マンションの一室を購入して賃貸希望者に貸し出すと、それだけで月々の家賃収入が得られます。
多額の元手が必要になるので初心者向けとはいえませんが、不動産ローンを組むこともできます。
月々のローン返済額よりも家賃収入が多くなれば、安定した運用が可能になるでしょう。
いきなり高額なローンを組むのが不安な方は、REIT(不動産投資信託)からスタートするのも方法のひとつです。
6. ソーシャルレンディング
ソーシャルレンディングとは、融資を望む企業と投資家をマッチングするサービスです。
投資家は、サービス会社に掲載されている融資先を選び、投資する金額を決定するだけで簡単に申し込めます。
契約満了日を迎えると元本と利息を受け取れる仕組みです。
銀行預金と同じくらい手軽で、簡単に儲けられるイメージが強いソーシャルレンディングですが、前述したように貸し倒れリスクがあるため、決して初心者向けの運用方法ではありません。
利用する際は、サービス会社と融資先の信頼性をしっかりと確認しておきましょう。
SBI証券は、初心者向けのみならず中級者向けの運用方法にも対応しています。
特に、最初にご紹介した個別株投資に関しては、国内株・海外株ともに銘柄数が豊富で、その株は業界トップクラスを誇ります。
いろいろな運用方法にチャレンジしてみたい方は、SBI証券をチェックしてみてはいかがでしょうか。
資産運用するにのおすすめの証券会社
資産運用や投資をするにあたって、以下の証券会社の口座を取得しておくことをおすすめします。
これらの証券会社は、株式投資やFX、投信積立などで利用する機会が多いためです。
- SBI証券
- 楽天証券
ここでは、それぞれの特徴やメリットを詳しく解説します。
SBI証券

| 取扱商品 | 国内株・米国株・新興国株 投資信託・ETF FX 国内債券・外国債券 金・プラチナ・銀 など |
| 取引手数料 | 国内株(スタンダード):55円~ 国内株(アクティブ):0円~ 米国株:0.495% 投資信託:無料(信託報酬は別途発生) |
| 取引ツール | HYPER SBI 2 SBI証券 株 アプリ SBI証券 米国株 アプリ など |
| ポイント投資 | ○(Tポイント・Pontaポイント・dポイント) |
| NISA | ○ |
| iDeCo | ○ |
| 公式サイト | SBI証券 |
| 関連記事 | SBI証券の評判 |
SBI証券は、910万以上の口座開設数を誇る国内を代表する証券会社です。
取り扱っている金融商品は株式やFX、投資信託、債券など多岐にわたります。
個別銘柄に至っても米国株が約6,000種類、投資信託は約3,000本と圧倒的です。
また、業界最安値クラスの手数料を提示しているため、可能な限り運用コストを抑えたい方におすすめです。
SBI証券が提供している「HYPER SBI 2」という取引ツールは、40種類以上のテクニカル指標を備えています。
初心者の方はもちろん、短期的な利益を得たい中~上級者の方にも向いています。
詳しくは、SBI証券公式サイトをチェックしてみてください。
楽天証券

| 取扱商品 | 国内株・米国株・新興国株 投資信託・ETF FX 国内債券・外国債券 金・プラチナ・銀 など |
| 取引手数料 | 国内株(超割コース):55円~ 国内株(いちにち定額コース):0円~ 米国株:0.495% 投資信託:無料(信託報酬は別途発生) |
| 取引ツール | マーケットスピード iSPEED 楽天MT4 など |
| ポイント投資 | ○(楽天ポイント) |
| NISA | ○ |
| iDeCo | ○ |
| 公式サイト | 楽天証券 |
| 楽天証券の評判 |
楽天証券もSBI証券と同じく、多彩な金融商品と最小限の取引コストに強みを持ちます。
ただし、楽天証券の場合は資産運用によって楽天ポイントが貯まり、それを再投資できます。
また、投信積立では楽天キャッシュで決済できるのも特徴です。
楽天経済圏で積極的にポイ活を行っている方には、SBI証券よりも楽天証券が使いやすいでしょう。
資産運用・投資に関するよくある質問
最後に、資産運用や投資に関するよくある質問をご紹介します。
- そもそも資産運用はしないほうがいい?
- 事前に資産運用のシミュレーションはできる?
そもそも資産運用はしないほうがいい?
資産運用は行うべき、しかもなるべく早い段階でスタートすべきだといえます。
現在の日本は低金利政策が長らく続いているため、銀行預金だけではほとんど資産が増えないためです。
また、金利が低くなると円安が進行しやすくなり、日本円の価値が低くなってしまいます。
いままで100円で買えていたものが、10年後には150円出さないと購入できない可能性もあるため、日本円の価値の目減りを補うためにも何らかの資産運用が必要です。
もちろん資産運用をするかどうかは選択肢のひとつにしかすぎないため、さまざまな情報を調べたうえで判断を行ってみてください。
事前に資産運用のシミュレーションはできる?
長期投資を行う予定がある方は、金融庁の「資産運用シミュレーション」を活用することをおすすめします。
「毎月の積立金額・想定利回り・積立期間」を入力するだけで、元本と運用収益の推移を一目で確認できます。
たとえば、「毎月の積立金額50,000円・想定利回り3%・積立期間10年」で設定した場合、10年後の元本は600万円、運用収益は約98万と算出されます。
あらかじめ目標金額を定め、そこから逆算して月々の積立金額を決めると良いでしょう。
初心者向けの資産運用のまとめ
今回は、おすすめの資産運用・投資方法や適切な選び方をご紹介しました。
- 資産運用の手段には、投資レベルに合わせたさまざまな方法が存在する
- 初心者の方にはNISAやiDeCo、投資信託、ロボットアドバイザーなどがおすすめ
- 中級者の方には個別株投資やFX、仮想通貨、不動産投資などがおすすめ
- それぞれ仕組みや性質が異なるため、リスクリターンや運用コスト、運用期間などの基準をもとに選び分けよう
- 失敗を避けるためには、少額投資や分散投資といった工夫が必要
資産運用の数ある方法を理解しておくと、さまざまな選択肢のなかから自分に合うものを選べるようになります。
まずは自分の投資レベルを初級から中級まで分類したうえで、リスクリターンや運用コストなどを比較しながら最適な運用方法を選び分けましょう。
できるだけ早いタイミングでスタートするほど、資産運用で得られる恩恵が大きくなります。
これから資産運用や投資を始めるなら、取扱商品点数や銘柄数が豊富なSBI証券をチェックしてみてはいかがでしょうか。
取引手数料が業界最安値クラスに設定されているため、コストを抑えながら、幅広い金融商品を使って資産運用を楽しめるでしょう。